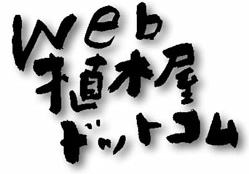 |
石造品の紹介 飛鳥時代になって、仏教が伝来しその後の隆盛とともに仏像、献灯用具としての灯籠、供養としての石塔など石造品が数多くつくられ、桃山時代になり茶道の祖千利休をはじめ茶人の人々によってこれらの石造品が茶庭に持ち込まれました。 江戸時代になるとこれらの石造品が大小の庭園に用いられ、このように一般に普及してくると古くからの石造品では足らなくなり、古い由緒ある石造品を模倣したり、新しいものを考案したりして現在に至っています。 |
| 手水鉢のコーナー 自然石手水鉢 UP 見立物手水鉢 創作手水鉢 |
露地の第一が蹲踞であり、その中心が手水鉢である。茶会を催すにあたり、亭主も客も蹲踞で手水することにより、茶事が始まるとされる。それ故に、多くの茶人たちは、自分の理想とする侘び幽玄の世界に合った手水鉢を求めて好みとした。飾り手水鉢も同様である。 手水鉢はその作り方から三種類に分類することが出来る。自然石にそのまま水穴を穿った自然石手水鉢・石造品を応用して穴を穿った見立物手水鉢・人工的に新しく作り出した創作手水鉢の三種がある。 |
石灯籠のコーナー 織部形灯籠 活込石灯籠 石 燈 籠 石 造 品 |
さきに記しましたが、灯籠は元来仏様に火を供えるためであったものを、茶庭に取り入れ、その後庭園の添景物として用いられるようになりました。 |
| 庭石のコーナー 木曽駒石・佐治石 鞍馬石・丹波鞍馬石UP 茶席・蹲踞廻等役石UP |
石材・庭石の紹介 京都では鞍馬から産出する鞍馬石と丹波地方より産出する丹波鞍馬石とに大別される。鞍馬から産出する鞍馬石を本鞍馬(本鞍)という、丹波鞍馬石(丹鞍)・山梨県産の甲州鞍馬石(新鞍)に対してこれが本場ものである。 本鞍馬石は京都市の鞍馬より産し、地表下にあるものを掘り出して採取する。今日では良質のものの産量が減じたが、昔の庭ではこれを使うことを誇りとしていた。石質は黒雲母花崗岩で特に酸化鉄の存在により玉葱状剥離が現れ、鉄錆色が全面を覆っているのが上物とされる。製品としては、殆ど加工されていない、天然の形で沓脱石・飛石等に用い、時に水鉢として穴を穿った自然型手水鉢もある。現在は産出も少なく、殆ど丹波鞍馬石・甲州鞍馬石で代用されている。 丹波鞍馬石は、本鞍馬石と同じく、鉄錆色であるがサビ色の冴味が劣る。製品としては石の周囲を加工した物が殆どであり、自然のままの状態のものは石積用(野面積)として利用されている。関西地方では需要も多く本鞍馬石の代用として利用されているが、近年、良質の物が減少している。 |
| |Web植木屋ドットコム /庭園資材卸 弘農園| | |